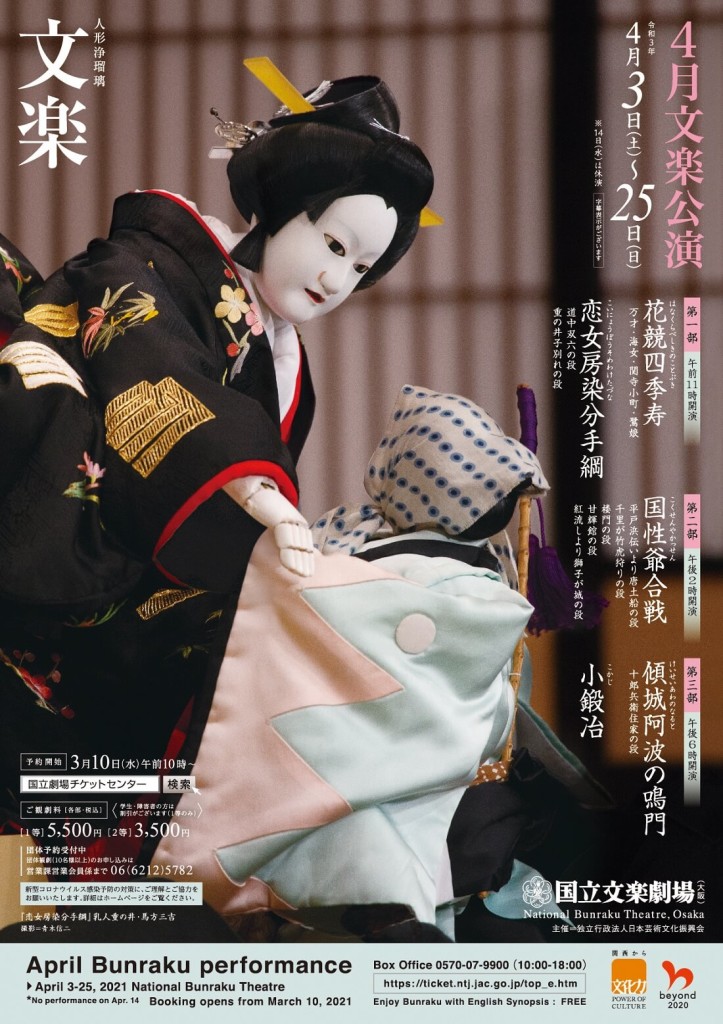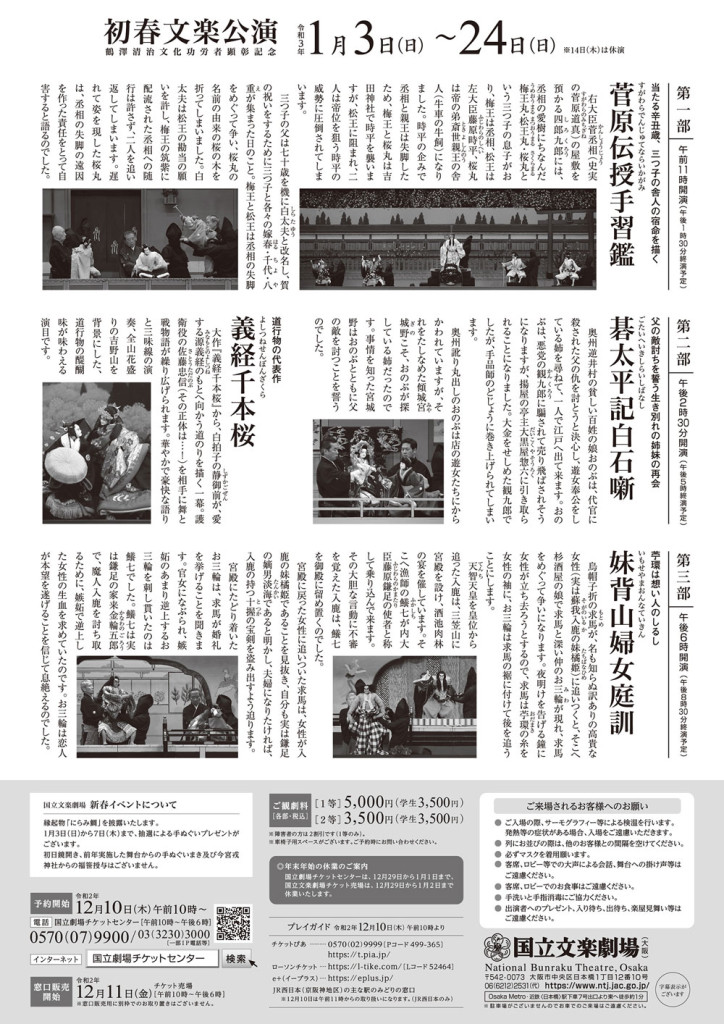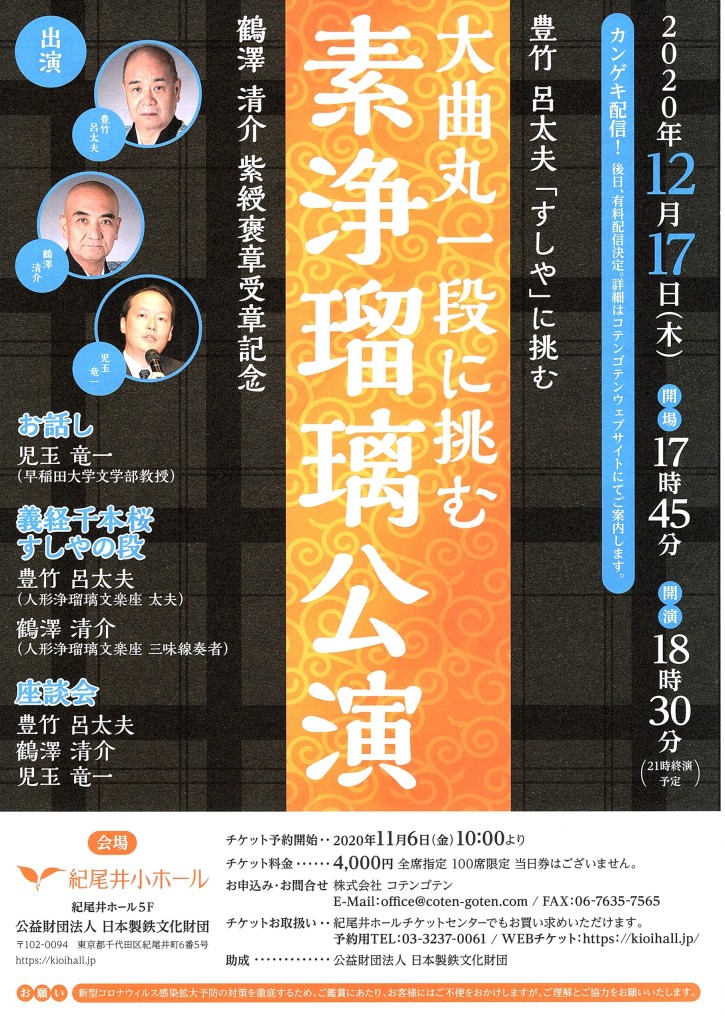森田 美芽
この災厄は、いつ終わるのだろう。多くの人がそう思い、そして無事を祈る。あまりに長いその忍耐の時に、心が倦み疲れ、まして夏の無聊を慰めてくれる浪花の夏祭も中止または縮小とあれば、この猛暑と悪疫に立ち向かう心の憩いすら見当たらない。
だから、劇場に向かう。そこにいる人々が、その圧倒的な熱量が、心の底にとどまる氷塊を溶かしてくれることを期待して。
第一部は恒例の「親子劇場」。今年の演目は『うつぼ猿』『解説 文楽ってなあに?』『舌切雀』。最初に亘太夫による約3分の解説。子どもにも真っすぐ通じる、ということは、本質的で、しかも子どもの世界を広げるものでなければならない。その困難への挑戦を力強く思う。
『うつぼ猿』は、狂言よりも猿曳の深い情愛、やさしさ、猿の無邪気さの描出に目が行く。
籐太夫の猿曳が情愛にあふれ、芳穂太夫が愚かだが後味悪くない大名を、津國太夫が両者の間で悩む太郎冠者を子どもたちにも届くように、丁寧に語る。初舞台の聖太夫、薫太夫らも、最初は恐々声を出していたような感じが、「俵を重ねて面々に」など、負けじと声を張っていたのに好感を持った。三味線は清友がシンで、團吾、友之助、燕二郎、清方と、手堅くまとめる。人形では文司の猿曳がやはり温かさを感じさせ、文哉の大名も嫌味なく、紋吉の太郎冠者が悲哀を感じさせ、猿は勘介・玉路で、愛らしい猿の仕草に温かい拍手が起こる。
『解説 文楽ってなあに?』簑太郎と勘次郎。内容はいつもの人形解説。やはり客席からでは人形の首の面白さが見えにくい。そこだけでも拡大した映像を出した方がよいかもしれない。
『舌切雀』は、小住太夫、亘太夫、碩太夫という若手トリオ。小住太夫のお竹は達者なところを聞かせ、亘太夫は人の良い爺そのままに、親雀の碩太夫は、まだ声の使い方が単調に聞こえる。いまや中堅の清志郎が三味線を導き、清丈清公、清允らを引っ張る。なんと心地よく、その勢いが心に届くことか。
親雀は貫禄十分だが、小雀たちは実に愛らしい。翼を広げていっぱいに踊る姿で、前半の不気味さも中和される。もちろん、筋立がやや単純すぎるきらいはある。おそらく文楽を見に来る子どもたちは、少なくとも小学校3年生以上という感じの子が多いから、これでは内容的に物足りないと感じるのではないだろうか。すると見どころは、やはり葛籠の中の化け物との対決ということになるが、大蛇、怪鳥、骸骨、それに今年の時事ネタは大谷翔平。オリンピックにしなかったのは、やはりコロナに苦しむ人の多い大阪での配慮か。玉助の婆が悪役らしく、勘市の爺の人の良さと正反対。紋秀の親雀が貫禄十分。勘次郎の子雀が愛らしく、勘介、玉路、和馬、簑之らも総踊りと宙乗りで沸かせる。
第2部「生写朝顔話」の半通し。こうした場合、よく出る「宇治川蛍狩の段」を略し、「薬売りの段」「浜松小屋の段」を入れる。そうすることで、この物語全体の印象がはっきりと違ったものになる。
「明石浦船別れの段」 清治の糸が、一瞬で月明りに惑う夜の海に誘う。呂勢太夫は「せめて慰むよすがもと、掻き鳴らしたる糸調べ」に、深雪の思いの深さ、会われぬ苦しみを感じさせる。そして思いがけない出会いとつれない別れの嘆きを見事に描く。
深雪の勘十郎の思い詰めた積極性と阿曾次郎の和生の歯切れの悪さが対照的簑悠の船頭、最初は両手の表情が堅い。船上の二人、異なる思いと時間が流れるのがわかる。途中から、主人の行動に困り、照れるところがうまくなった。
「薬売りの段」希太夫、勝平。はずむ息、明るくよく響く音。「かたげて走る」などのリズムの変わりや、『行こか参らんしよか』の唄、桂庵の長い口上の面白さもよく勉強している。
笑いの一幕のようで、手を消毒したり、参詣人が集まると「密です」の看板を出す。このあたり簑一郎がうまく遣った。
続いて「浜松小屋の段」呂太夫、清介。零落した深雪の出。いまならタブーの障がい者いじめ、禁止用語のオンパレード。それほどの屈辱を受けながら、なお生きようとする深雪の執念と、その誇り。乳人浅香もまた、辛苦を重ねてここに出てきたとわかる。深雪のためらい、名乗ることのできない苦しみに、浅香もまた、嘆きのうちに故郷の母の死を告げる。深雪が、自らの境涯を嘆き親を苦しめたことを悔いる、そして浅香との再会。しかしそれを妨げる輪抜吉兵衛。立ち回りのメリヤスが入り、瀕死の浅香が生き別れの親のことを告げ、「大井川の段でなぜ戎屋徳右衛門が自害するのかの理由がここで語られる。
その痛ましさ。実は、この場が出ることで、初めてこの物語の輻輳するドラマの奥行が見える。深雪がストーカー的に阿曾次郎を追いかけることばかりが目につくが、実は深雪自身がこの恋を貫くために、自らも危険にさらされたり、遊女に売られかけたり、散々な目に遭う。それを助けるのが、実は阿曾次郎ではなく、こうした家来たちの忠義の物語であり、また生き別れの娘と父の絆、深雪を介して、会うことのできなかった二人が冥途で出会うという伏線が引かれる。
深雪と阿曾次郎の恋の陰にある、家臣たちの、それも二代にわたる忠誠の証。その犠牲の上に、彼女の恋は後に成就する。そのもう一つの主題、親子と主従の絆の深さを見せることができたのは、言うまでもなく、呂太夫の的確な浄瑠璃世界の把握に基づく確かな語りである。とりわけ、一度は身を偽って突き放した浅香に向かって呼びかける詞、「浅ましい浅ましいこの形で」の一言に息を飲み、「海山超えて憂き苦労」が迫ってきた。「お果てなされた母様の死に目に遭わぬのみならず」の嘆きが深まる。ここで呂太夫は、わざと調子をいなした声で絶叫する、その詞の一つで、深雪の苦悩が、また浅香の、亡き母の嘆きまでが一つになる。それを包み込むような、浅香の芯の通った強さと優しさ。一切を解さずただ己が欲望にのみ忠実な吉兵衛。その的確な人物描写を支える、哀れな二人の運命に寄り添うような、清介の糸。
簑志郎の輪抜吉兵衛、悪役の性根、ふてぶてしさの描出が見事。勘彌の浅香は、前半動きが少ない所も、思いやりと忠義に溢れ、後半の女丈夫の強さで芯の通った乳人像を描いた。
「嶋田宿笑い薬の段」は中の南都太夫、清馗がよく動く明快な詞で面白く聞かせる。南都太夫は萩の祐仙のおかしみを語り、清馗は人物の表情まで見えるような達者な三味線。
奥、咲太夫、燕三。切場ではないが、ここは咲太夫しかない、という配役。今回、徳右衛門の性根がよく見えたので、祐仙の軽薄さがより際立った。しかし笑い薬の笑いが、今回は長く感じてしまった。客席の反応が静かすぎるせいもあるが、笑いが舞台を包んで客席を揺るがすような、そんな広がりにならない。それは私たちの中で、あまりに長く、笑うことが許されなかったためだろうか。
祐仙といえば勘十郎の持ち役のように思えていたので、簑二郎の祐仙は驚きだったが、舞台を広く使い、自在に動き、笑いが止まらない表現もきっちりこなす。ただあとは自分の役柄への自信のみかと見た。
「宿屋の段」前段と打って変わって、阿曾次郎、この場では駒沢の深いもの思いに始める。深い余情をたたえた富助の糸に導かれ、千歳太夫も駒沢の詞に情を込める。朝顔の女が深雪と気づき、それとなく彼女をかばい、助けようとする、ただそれが深雪の熱量に比べ、あまりに冷静なように感じさせるところは、また彼も狙われる身のゆえであるとわかる。去り際の「テ残念至極」の詞に底力を感じた。ただ、徳右衛門の詞がやや世話に傾いたように感じた。
「大井川の段」靖太夫、錦糸。
ここからは一気に結論に向かう。こんな艱難辛苦を経てまで恋い慕う夫を目の前にしていながら、なぜ気づかなかったのか。深雪の口惜しさ、そしてここで情熱を爆発させる強さを、靖太夫は一気呵成に語る。錦糸は終始冷静に背景を描く。
ここでいつも徳右衛門が自害することが解せなかったのが、先の「浜松小屋」と結びついて、徳右衛門の人物像も深まる。今回の勘壽の徳右衛門は、その人の良さがどこから来たのか、父としてどのような思いであったかも感じさせる好演。
そして勘十郎の深雪。極めつけともいうべき簑助師の「朝顔」を受け継ぎ、その一途さ、情熱、零落しても誇りを忘れず、芸人となって自らの境涯に恥じらうところも見事。和生の阿曾次郎が、深雪に引きずられるようで、しっかりと自分の公的な立場をわきまえつつ行動している冷静さと賢明さ、そしてふと見せる優しさが、この人らしい。玉彦の手代松兵衛、簑太郎の下女お鍋もちょっと笑わせるところがよく、玉輝の岩代は骨のある敵役で、阿曾次郎の苦衷を理解させる出来。玉勢の奴関助もさわやかな印象。
第三部の『夏祭浪花鑑』極めつけ、夏の定番。あまりの名作で、しかも夏の暑さを吹き飛ばすような力演で、おそらく誰もが引き込まれるエネルギーに満ちている。
様々な浪花の夏の風情を背景に、祭りの興奮と狂気が交錯する中での殺人事件。その背景は、高津神社の夏祭である。その近しさゆえに、大阪人はこの物語を愛し、また親しむ。今なら半グレなのだろうが、そこに貫かれる意地は、いまも大阪の地に脈々と伝わる。しかし、「内本町道具屋の段」を省略したことで、やはり物語が単純になりすぎたきらいはある。
「住吉鳥居前の段」口、碩太夫、錦吾。碩太夫は声も大きく、精一杯の姿勢はいつも気持ちよい。まだ声は一色しか出ないという感じ、特に釣船三婦のような貫禄は難しい。「丸う捌いた男伊達、美しいので気味悪く」の変化はまだ。錦吾は落ち着いてしっかりと弾いている。
奥、睦太夫、團七。睦太夫は安心して聞ける。多様な人物の語り分けなど、自然に流れる。三婦だけでなく、団七も徳兵衛も、さらにこっぱの権やなまの八などにも、血が通う。ただ、碩太夫もそうだが、大阪の香りというか、そういう感覚的な部分まで求めるのは難しい。かつて故小松太夫でここを聞いたとき、住吉の風情、町の賑わい、住吉の反橋に響く蝉の声や日差しの暑さ、さらに黄昏の町の香りまで感じたことがある。浄瑠璃の生活世界とは、そういう時空の広がりを包むものであることを知らされた。これは作り事であっても、現在に通じる感覚を伝えているのだと思う。團七はそうした懐かしさを心に描かせる魅惑的な糸。
「釣船三婦内の段」口、咲寿太夫、寛太郎。磯之丞と琴浦のやり取りが、何とも言えずつきづきしい。「据ゑ膳と鰒汁を喰はぬは男のうちでは」の強がりなど、思わず微笑んでしまうほど。寛太郎の突っ込み、まるで会話をしているかのような的確さで入る。
奥、錣太夫、宗助。この人は、切れ味よりも情の深さが勝る。お辰の詞も、そのイキだけでなく、夫の顔を立て、周囲を立てる気遣いや、夫の面目を失わせないでよかった、という感情が伝わる。これは清十郎のお辰の表現にも当てはまる。簑助師のお辰の気風のよさや潔さよりも、そうしたいじらしさや、恥じらいといった風情が伝わってくる。また義平次のアクの強さも。宗助もこの人とのコンビネーションが板についている。構成の確かさ、ふとした感情の表し方も。
「長町裏の段」団七を織太夫、義平次を三輪太夫、三味線は藤蔵。
必死で追いかける団七、この憎々しい義平次。義理の親子とはいえ、義理と金に絡んだ対立、しかもこの義平次のブラックな表情。団七をいたぶる意地の悪さ、挑発。草履で顔をはたく、ここまでやられては黙っていられない、追い詰められていく団七が切れ、「毒喰はば皿」とついに刃を向ける。その怒りを生み出し、また挑発する三輪太夫のうまさ。織太夫は、団七が怒りを溜めていき、それが切れる一瞬の凄まじさを爆発させる。
丸胴に刺青、長い手足、不思議なバランスで、その大きさ、ダイナミックさが強調される。
しかし殺し場は、スローモーションのようにゆっくりと、そして義平次のしぶといこと。泥にまみれても、この人は簡単に死にそうにない。その団七と義平次が絡み合う向こうで、過ぎていく夏祭の提灯。いまも西成区の生根神社に残るこの「だいがく」は、古い祭りの形を表わしている。そして「ちょうさ、ようさ」の掛け声とともに現れる神輿のスピーディなこと。人形遣いが神輿の台を振り回すように、人形もそれにつれて振り回される。その騒ぎに紛れて逃亡しようとする団七。「八丁目、差して」が圧倒的。
人形では、玉男の団七が圧巻。この不器用な男の生きざまを共感させる遣い方。玉也の三婦の貫禄と、積み重ねてきた経験の重さ。お梶の一輔も小気味よく、玉翔のこっぱの権と玉誉のなまの八もいいコンビ。清五郎の磯之丞はほんまにぼんぼんやなあと感じるし、紋臣の琴浦は健気で品のよい娘のよう。亀次の佐賀右衛門のうまさ、一目でその性根がわかる。勘昇(後半玉征)は倅市松を愛らしく遣い、玉延(後半玉峻)の役人もしっかりと見せる。一寸徳兵衛は玉佳、玉男の団七と並んで引けを取らないスケールが出てきた。おつぎは簑二郎と勘彌の変わり(所見時は簑二郎)でどこかに「極妻」を経験した柔らかさ。玉志の義平次の憎々しさが、このドラマを最高潮に盛り上げる。
夏が終わる。そしてまた、忍耐の日々が始まる。
「失われたものはかえってこない
何が悲しいったって、これほど悲しいことはない」
(中原中也『黄昏』より)
ひとたび失われれば帰ってこない。それほど大切なものを私たちは与えられているのだ。文楽に限らず、この国を支えてきた人々の業が、仕事が、暮らしが。分けても、舞台芸術が「不要不急」のように扱われ、また人々にも、それがなくて済ませられる贅沢のように、甚だしくは諸悪の元凶のように扱われ、それほどでなくても、人々の心から、それを受け止める余地が失われていったことは否めない。
そうした文化の「不在」に対して、私たちは次第に鈍感になりつつある。「去る者は日日に疎し」と言わんばかりに、目からも遠ざかる者に我々は冷淡である。また多くの人々が、その日の暮らしに、また病のための困難に、「それどころではない」状況にある。だからこそ、残さなければならないものがある。
今回、この舞台を見て、そして呂太夫の浄瑠璃を聞いて、改めて思ったことがある。文楽の時代物は、必ず主従の絆、親子の絆を無残に引き裂くものがあり、運命に翻弄される人間の苦しみがある。そうした根底にある浄瑠璃の文法ともいうべき世界観がある。そのうえで私たち現代人が共通に感じる悲哀や情が表現されるのに共感する。呂太夫の浄瑠璃を聞く時、その根底的な確固たるその世界の文法、世界観とそれを表現する音韻の法則としての節使いや語りの技法が揺るぎなくあって、その上に彼の理解した、普遍的な人間性を備えた登場人物の理解の表現がある。だから、江戸時代のことなのに、いま目の前に起こっているように、しかも全く違う世界観を描いているのに、今の世の人の思いに通じるものとして伝わってくる。それが古典としての厚みであり、語りの芸としての義太夫節の本筋であるから、どの演目であっても、その基本がきちんと、素人にも伝わってくる。驚くべきことと思う。
これがまた、残さなければならないものの一つであることに間違いない。
「不在」ではない、いま彼らはここに生きて、そして大切なものを守っているのだから。それはまた、これからも私たちすべての命を伸びやかに生かし、輝かせるものであるから。
掲載、カウント2021/8/12より)