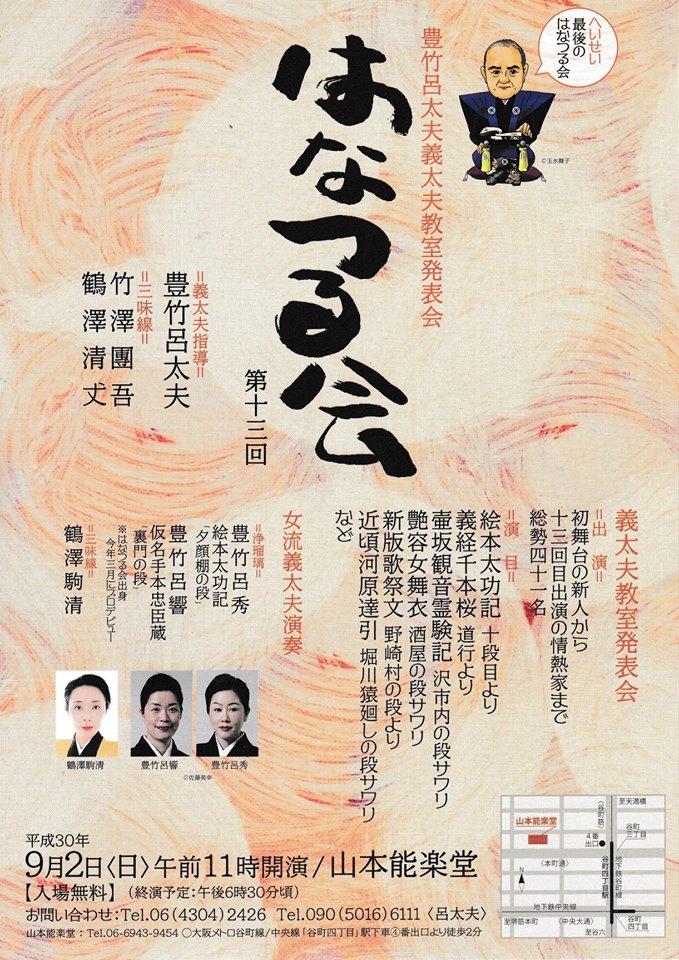森田美芽
国立文楽劇場第40回邦楽公演は、2018年8月18日、文楽素浄瑠璃の会として、豊竹呂太夫、鶴澤清友による『和田合戦女舞鶴―市若初陣の段―』、豊竹咲太夫、鶴澤燕三による『曲輪文章―吉田屋の段―』、そして咲太夫、片岡仁左衛門による対談「浄瑠璃よもやま話」が行われた。演目解説は大阪市立大学大学院の久堀裕朗教授。
対談の司会は産経新聞文化部の亀岡典子編集委員と、行き届いた顔ぶれで、舞台そのものの充実と、観客に伝えるものの両面において評価の高い会となった。

「和田合戦女舞鶴」は東京国立劇場でも1989年に上演されたきり。その前の記録をたどると、1965年に三越劇場、1950年に十代豊竹若太夫襲名披露狂言として上演されている。そのため、呂太夫にとっても、祖父の衣鉢を受け継ぎ、若太夫襲名という大きな目標のステップであることは間違いない。
彼はこの作品を、2009年に早稲田大学で、2015年国立劇場で素浄瑠璃で語っており、いずれも三味線は清友と、磨きをかけ、手の内に入れてきた、今回はその成果を問われることになる。また「越前風」と呼ばれる曲風を伝える貴重な一曲として伝承の上でも大きな意味を持つ。
「市若初陣」まず市若丸の登場。11歳ながら、錦革の鎧と兜、弓矢を携えた本格的な武者姿が浮かぶ。母に「逢ひたかった」という11歳の稚さ。息子を出迎え、手柄を立てさせたいと語る母。そこに「忍びの緒」の謎が現れる。はっとするような展開で、気が付けば物語の中に取り込まれている。
板額は市若をなだめ、気を取り直し、尼君のもとへ向かおうとする。そして尼君からの残酷な事実の語りに、「ホイ、はつ」と、忍びの緒に込められた意味を悟る。その重さを感じさせる語り。
そして尼君の懇願に、夫への恨みと嘆きが交錯する。「エエ聞こえぬぞや我が夫」からのこの板額の嘆き、「告げとも知らず余所の子の、花々しきを見るにつけ」の泣きの表現。それに対する夫の無責任、妻にすべての苦しみを負わせながら、という怒りも共にさせられていく。
そして「涙を忠義に思ひかへ」からの豹変。「ナニ、腹切つてか」「アノ腹をや。腹を」の畳みかける苦しみに、清友の撥が入る。
そして「耳聳立てし四方八方」の緊張感が高まる中での、板額の一人芝居。
その必死さの裏は嘆きと伝わる。そして市若が潔く腹を切り、苦しい息の下から母を呼ぶのに対し、母は「与市殿とわが仲の、ほんの、ほんの、ほんの・・ほんぼんの子ぢゃわいなう」と語りかける母の悲しみが臓腑をつんざくばかりに、複数の拍手がたちまち客席に広がる。
「なんの因果で武士の子とは生まれ来たことぞ」が胸に堪えた。
そこから二親が息子の首を手渡す涙。さらに言えば、この身代わりの犠牲そのものが無になってしまうというさらに残酷な結末が待ち受けている。
この場では、本当なら必要のない身代わりが必要と信じて、市若丸がその犠牲となっていく、そのプロセス自体があまりにも理不尽に思われ、「寺子屋」などのようには共感しにくい構造になっているにもかかわらず、なればこそ、市若の純真さ、いたいけな少年像が明確に、そしてそれを義理のために死なせなければならないという矛盾を背負った板額の嘆きと、母としての叫び、にもかかわらず「涙を忠義に思ひかへ」る男勝りの忠義心が、またそのことを強要する当時の論理の残酷さが心にすとんと落ちる。
呂太夫の語りはそれらの物語の起伏、板額と市若の親子の情と忠義の意志、それらの葛藤と悲劇を余すところなく描き、清友の糸が涙と嘆きに彩りを添えた。
「吉田屋」冒頭、暮れのざわめきと色町の風情を燕三が艶やかに描き出す。喜左衛門の詞の深み。長年色町の裏も表も知り尽くし、客を逸らさぬ手際、「紅絹裏の羽織をふわと」打ちかけるその軽やかさが目に浮かぶ。
藤屋伊左衛門の詞、「七百貫目の借銭負うて」「この身が金ぢや。総身が冷えて堪らぬ」の呼吸。
ところが夕霧に客があると聞いた途端に調子が変わる。こうした感情の機微も堪える咲太夫の語り。余所事浄瑠璃が入り、夕霧の出。二人のじゃらくらとした戯れ。そして15分に及ぶ夕霧のクドキ。
「この夕霧をまだ傾城と思うてか。ほんの女夫ぢゃないかいな」に込められた女心。段切れは「申し申し伊左衛門様」からの詞が義太夫として納まる。
そして仁左衛門と咲太夫の対談。
仁左衛門の巧まざる愛嬌とニンの良さ。咲太夫との縁、幼少期の思い出に始まり、松島屋系の「吉田屋」の演じ方、性根、演技についての苦労話など、また、文楽と歌舞伎の間での相互輸入のいきさつも興味深い。
しかしその中で、失われて色町の風情と、失われゆく義太夫のことば、義太夫訛りについて触れられた時は胸が痛んだ。
「義太夫節の本行を習いにきたのは孝夫さん(現仁左衛門)の世代まで」といい、いまは丸本ものの科白も習いには来ないという。知らない人が大勢になれば、「多勢に無勢」で、本物を知る人が異端となってしまう。
正しい本行に従って役を学ぶことが、歌舞伎の若手の継承で途絶えることは実に危機的である。それは、文楽の方にも言えることだが、正しい大阪弁のイントネーションや、「義太夫訛り」が伝わらなくなっていけば、文楽のみならず歌舞伎も含めて日本の伝統文化の危機となる。それがもはや危機感どころではなく、現実になりつつある。
伝えられるべきものが伝えられなければならない。先人から受け継いだものを、次の世代へと確実に手渡し、伝えていかねばならない。
こうした素浄瑠璃の会を国立劇場が持つことの意義はどれほど強調してもし過ぎるということはない。それだけでなく、いま、文楽の具太夫節自体が、わずか20名の太夫、三味線によって支えられているという現実。
その中で、咲太夫は戦前からの伝統を直接に継ぐ世代として最後の人であり、呂太夫もまた、越路太夫や春子太夫といった名人に直接師事し、八世綱太夫らに直接稽古を受けた最後の世代である。
彼らの受け継いだものを、若手は全力で受け継いでいかねばならない。ほどなく、若手素浄瑠璃の会がもたれるが、彼らに一段と自覚を促すと共に、国立劇場に、失われてはならない伝統の灯を継承する責任をよく果たしていくこと、そのための文楽公演であることをよく肝に銘じていただきたい、と願う。
まだまだ、受け継ぐべきもの、彼らが手渡すものは数限りなく、時間は迫っているからだ。その時のはざまに、こうした至芸を聴くことのできた幸いを心より感謝する。